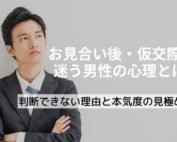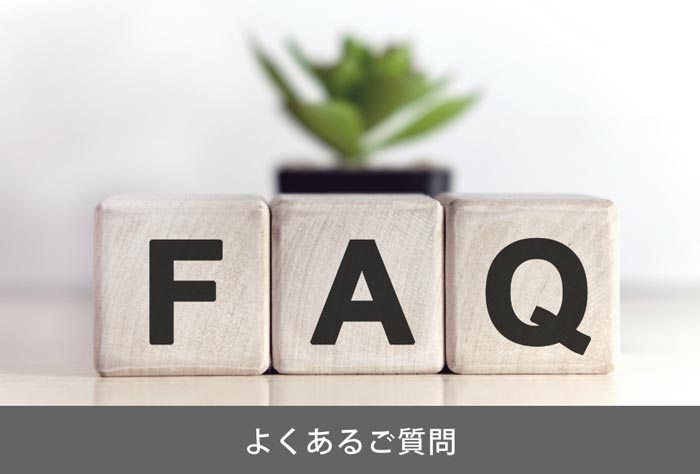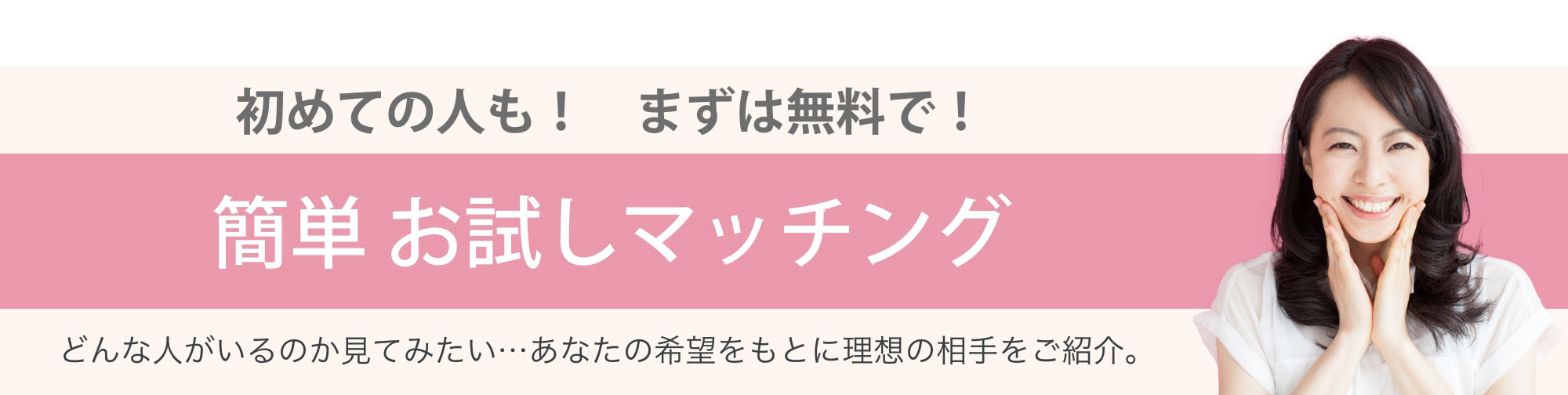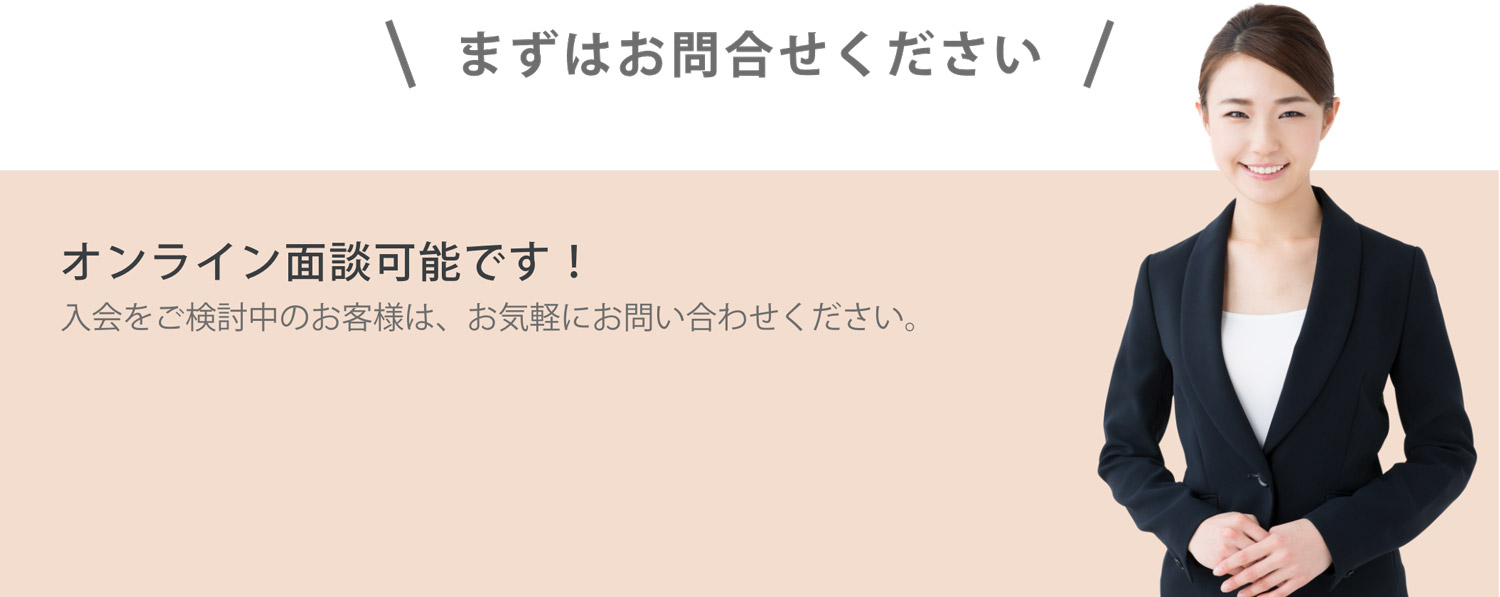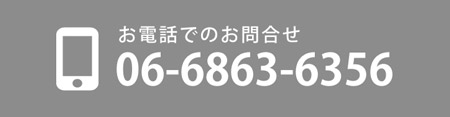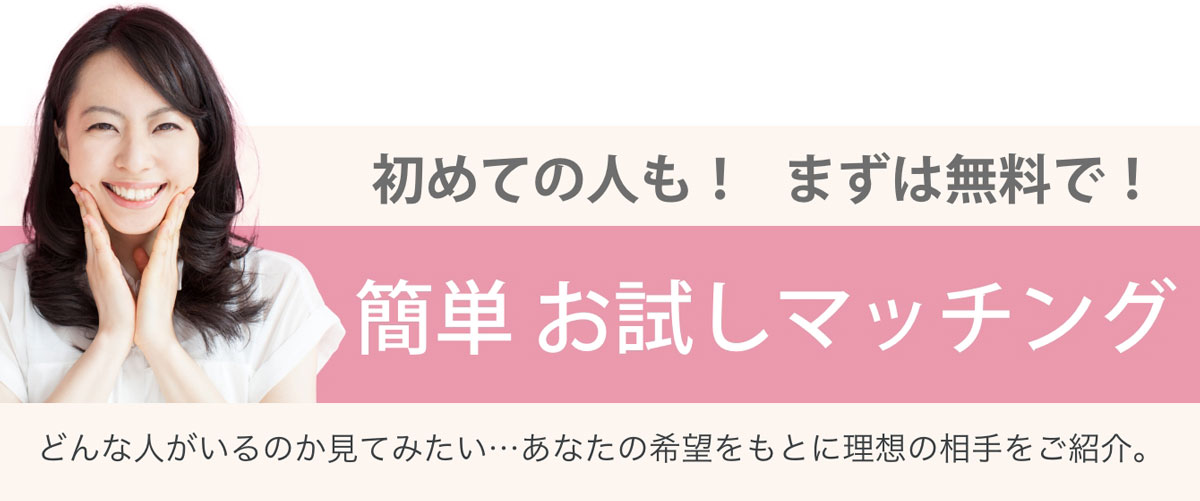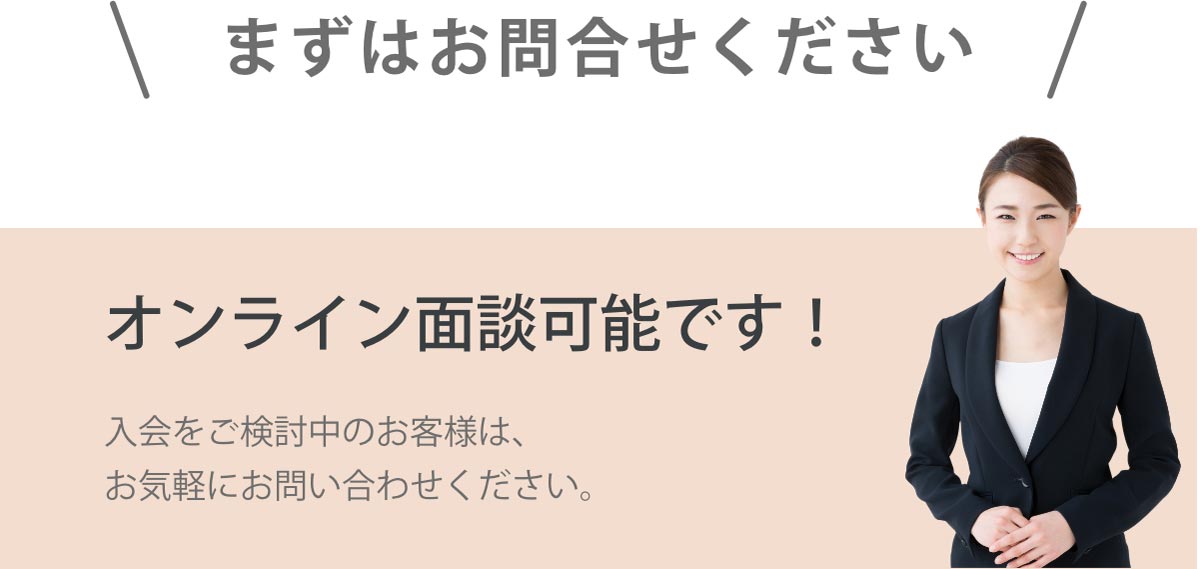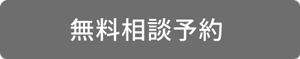嫁入り道具とは?昔と今の違い、そして現在の必要性は?
もくじ
- 嫁入り道具とは何か?
- 昔の嫁入り道具
- 現在の嫁入り道具
- 今は嫁入り道具がいらない?
- 初めての方は、「とよ婚。」無料相談、無料お試しマッチングから
- まとめ
結婚を考えている方にとって、「嫁入り道具」という言葉は一度は耳にしたことがあるかもしれません。
昔は、花嫁が実家から持参する家具や着物などが一般的でしたが、現代ではその考え方も大きく変化しています。
では、そもそも嫁入り道具とは何なのでしょうか? また、現在でも必要なのでしょうか?
本記事では、嫁入り道具の意味や歴史的背景を解説するとともに、昔と今の違いを比較し、現代における必要性について考察します。
さらに、自分にとって本当に必要なものを見極めるポイントや、準備の際の注意点についてもご紹介します。結婚準備を進めるうえで、無駄なく賢い選択をするための参考にしてください。

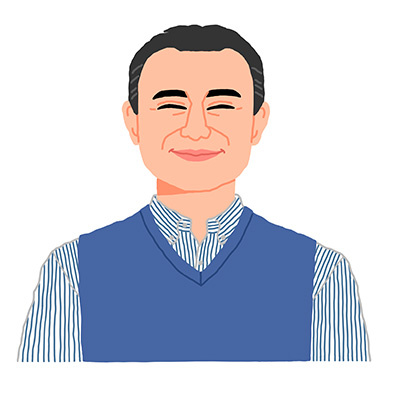
嫁入り道具とは何か?
「嫁入り道具」とは、結婚する女性が実家から持参する品々のことを指します。
昔は、新たな家庭での生活を始めるために必要なものを整えて嫁ぐのが一般的で、家具や衣類、家事道具などが用意されました。
これは、嫁ぎ先の家で円滑に暮らせるようにするためだけでなく、女性側の家の経済力や教養を示す役割も果たしていたと言われます。
歴史的背景と地域ごとの違い

日本における嫁入り道具の習慣は、江戸時代に武家や裕福な商家を中心に広まりました。
この時代、結婚は家同士の結びつきを強める儀式であり、嫁入り道具には新生活に必要な品々だけでなく、家柄の格式や経済力を示す意味も込められていました。
特に武家では、婚姻が政治的な意味を持つことも多く、質の高い調度品や着物、書物などを持参することで、教養や家の格を誇示する役割も担っていました。
明治・大正時代に入ると、結婚のスタイルが少しずつ変化し、一般家庭にも嫁入り道具の文化が定着します。
昭和の時代には、多くの家庭で婚礼家具や家電製品を一式揃えることが一般的になり、地域ごとの特徴も色濃く反映されるようになります。
例えば、関西地方では伝統や格式を重んじた「嫁入り行列」が行われ、東北地方などの寒冷地では実用性を重視した嫁入り道具が選ばれる傾向がありました。仙台箪笥は大正から昭和にかけて嫁入り道具として普及し、100年以上使い続けられているものも少なくありません。
現代では、結婚に際して「嫁入り道具」という考え方自体が薄れつつあります。家具や家電は新居に合わせて二人で購入するケースが増え、結婚を機に一から揃えるというスタイルも珍しくなくなりました。しかし、新生活をスムーズに始めるために必要なものを準備するという考え方は、形を変えながらも受け継がれています。
日本の結婚文化の変遷とともに、嫁入り道具のあり方も柔軟に変わってきました。伝統を重んじる家庭もあれば、実用性を優先する家庭もあります。
昔の嫁入り道具
かつての結婚において、嫁入り道具を整えることは欠かせない準備の一つでした。
特に女性の実家が用意することが一般的であり、婚礼家具や日用品、衣類など、結婚後の生活を支える品々は多岐にわたります。
これらの道具は単なる生活必需品ではなく、女性が婚家で円滑に暮らすための象徴であり、実家の経済力や品格を示す役割も果たしていました。
地域や家の格式によってその内容は異なりますが、特に重要視された代表的な嫁入り道具を詳しく見ていきましょう。
衣装箪笥(いしょうだんす)
衣装箪笥は、嫁入り道具の中でも最も重要な家具の一つでした。
一般的に桐(きり)材で作られることが多く、桐は湿気を防ぎ、防虫効果にも優れているため、大切な衣類を長持ちさせる役割を果たします。
衣装箪笥のデザインにもこだわりがあり、家紋が入れられることもあれば、漆塗りや金具で装飾された豪華なものも存在しました。
また、婚家に持ち込むことで「しっかりと生活を整えられる準備ができている」という証にもなり、嫁入り道具の象徴とも言える存在です。
合わせて読みたい
着物

着物は、嫁入り道具の中でも特に大切な品目の一つであり、女性が婚家での新生活を迎えるための必需品でした。
一般的に、婚家での生活や冠婚葬祭に備えるため普段着から礼装までさまざまな種類の着物が揃えられたようです。
特に格式のある家では、訪問着や留袖、喪服、さらには華やかな振袖なども含まれることがあり、花嫁としての品格を示す意味合いも持っていました。
また、実家から持参する着物には、母親や祖母から受け継がれたものもあり、家の歴史や愛情を伝える役割も果たしていると言われます。
布団

新婚生活を始めるにあたり、布団も重要な嫁入り道具の一つでした。
昔は、寝具を持参することで婚家での生活の基盤を整えると考えられており、特に質の良い綿入りの布団が選ばれることが多かったようです。
布団の種類や柄には縁起を担ぐ要素も多く、例えば鶴や亀、松竹梅などの吉祥文様が施されたものが人気で、これは「夫婦円満」「長寿」などの願いを込めたものであり、単なる寝具以上の意味を持っていました。
婚家で快適に眠れるようにと、両親が愛情を込めて準備していたという側面もあるでしょう。
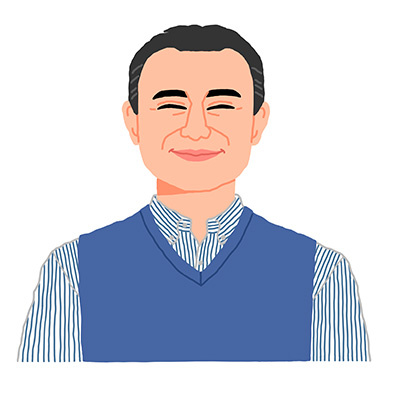
合わせて読みたい
食器
婚家での食生活を支えるために、食器も重要な嫁入り道具の一つでした。
漆塗りの重箱やお椀、箸などが一般的に持参され、特に婚礼の席で使用される美しい食器が選ばれることが多かったようです。食器の選定には、家の伝統や地域性が反映されることもありました。
例えば、関西地方では金箔をあしらった華やかな漆器が好まれ、東北地方では実用性の高い陶器が中心。
また、実家で長年使い慣れた食器を持参することもあり、新しい家庭での生活に安心感を与える意味合いもあったと考えられます。
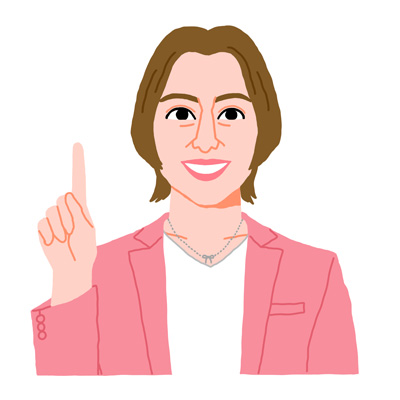
合わせて読みたい
針箱
裁縫道具を収納する針箱も、昔の嫁入り道具として欠かせないものでした。
結婚後の女性は家庭内の裁縫を担当することが多く、衣類の手入れや修繕に必要とされていたためです。針箱は単なる実用品にとどまらず、美しい装飾が施されたものもありました。
特に、漆塗りや金細工を施した豪華な針箱は、実家の格式を示す一つのシンボルでもあります。
また、結婚後も長く愛用され、親から娘へと受け継がれることもあったため、単なる道具ではなく「家族の歴史を刻む品」としての価値も持っていました。
ここまで挙げてきたものの他にも、嫁入り道具として持参されることの多かった品々がありました。
- 屏風(びょうぶ):部屋を仕切るだけでなく、装飾品としても使われることが多かった。華やかな柄や金箔を施した屏風は、格式の高い家庭で特に重宝された。
- 鏡台(きょうだい):女性が身だしなみを整えるための必需品であり、婚家での生活に馴染むための象徴とされた。
- 経机(きょうづくえ):仏壇に供える品を置くための小机で、信仰を重んじる家庭では特に大切にされた。
こうした嫁入り道具は、単なる生活用品にとどまらず、新しい家庭での幸せな暮らしを願う家族の思いが込められているものが多く、時代とともにその形は変わりましたが、嫁ぐ娘の幸せを想う両親の気持ちや、結婚に際して何かしらの準備をするという考え方は、現代にも通じるものがあります。

合わせて読みたい
現在の嫁入り道具
現代では、結婚生活のスタイルが多様化し、昔ながらの嫁入り道具をそのまま用意するケースは少なくなりました。
かつては、実家が婚礼家具や日用品を一式揃えて持たせることが一般的でしたが、現在は夫婦二人で新居に合ったものを選ぶスタイルが主流です。
しかし、新生活をスムーズに始めるために必要なものを準備するという考え方は、現代にも受け継がれています。
昔の嫁入り道具が家の格式を示す役割を持っていたのに対し、現代では「実用性」と「快適さ」を重視する傾向が強くなっています。では、具体的にどのようなものが準備されるのか、詳しく見ていきましょう。
現代の嫁入り道具の例
現在では、新生活を快適にスタートさせるために、以下のようなアイテムが嫁入り道具として準備されることが多いです。
- 家電製品(冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなど)
- 家電小物(掃除機、アイロン、炊飯器など)
- 家具(ベッド、ソファ、ダイニングテーブルなど)
- 日用品(食器セット、鍋・フライパン、タオル類など)
- 冠婚葬祭用品(礼服、数珠、ふくさなど)
これらのアイテムは、結婚する二人のライフスタイルや住環境に合わせて、必要なものを選ぶことが重要です。それでは、それぞれのアイテムについて詳しく見ていきましょう。
家電製品、家電小物

現代の新生活において、家電製品はなくてはならない必需品ですね。
特に 冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ の3つは、生活の基盤となる家電として、多くの新婚家庭で最初に揃えられます。
冷蔵庫がなければ食材の保存ができず、洗濯機がなければ日々の洗濯に困り、電子レンジがなければ簡単な調理も難しくなります。
これらは結婚と同時に用意することが多い傾向です。
また、掃除機・炊飯器・アイロン などの家電小物も、快適な生活を支えるために欠かせません。
特に、忙しい共働き夫婦の場合は、時短家電(食洗機、ロボット掃除機、電気圧力鍋など)も揃えることで、家事の負担を減らすことができるでしょう。
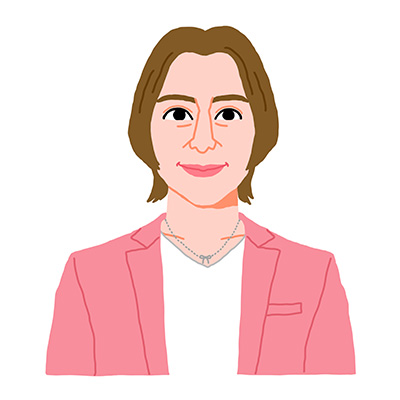
合わせて読みたい
家具
新生活を快適にするために、家具も重要なアイテムの一つです。
特に ベッド・ソファ・ダイニングテーブル などは、新居の広さや生活スタイルに合わせて選ぶ必要があります。例えば、ワンルームや1LDKのコンパクトな住まいなら、収納付きのベッドや折りたたみ式のダイニングテーブルが便利です。一方で、広めの新居に住む場合は、大きめのソファやダイニングセットを揃え、リラックスできる空間を作るのも可能ですね。
また、収納家具も大切なポイントです。クローゼットが少ない部屋では、衣類を整理するためのチェストやハンガーラックが必要になることもあります。
結婚前にどのような生活スタイルを望むのか、二人で相談しながら家具を選ぶことが大切です。

合わせて読みたい
日用品

結婚後の生活をスムーズにスタートさせるために、日用品の準備も欠かせません。
特に 食器セット・鍋・フライパン・タオル類 などは、毎日の生活に直結するため、パートナーとも話し合って気に入ったものを早めに探しておくと安心。
食器は夫婦二人分だけでなく、来客用も含めて最低限揃えておくと便利です。
また、料理をする家庭では、フライパンや鍋、包丁、まな板などのキッチン用品も必需品となります。
最近では、ペアのカップや食器セットを贈る親も多く、新婚生活のスタートにふさわしい贈り物として人気があります。
また、バスマット、シーツなどの寝具も、結婚を機に新調する人が多いです。
こうした日用品は、生活を快適にするために必要不可欠なアイテムであり、意外と後回しにしがちなので、早めに準備するといいでしょう。
合わせて読みたい
冠婚葬祭用品

結婚すると、親戚付き合いや冠婚葬祭に出席する機会が増えます。そのため、礼服・数珠・ふくさ などを事前に準備しておくことで、いざという時に慌てずに対応できます。
例えば、結婚式や親戚の集まりに出席する際には、フォーマルなスーツやワンピースが必要になります。
また、弔事の際には、喪服や黒のバッグ、数珠、ふくさ(香典を包む布)などが必要になるため、結婚を機に一式揃えておくと安心です。
特に、若い夫婦は突然の弔事に備えて喪服を用意していないことが多いため、結婚を機に一度チェックしておいてはいかがでしょうか。夫婦共に必要になるものなので、事前に準備しておくことで、いざという時に焦らず対応できますよ。
合わせて読みたい
今は嫁入り道具がいらない?
かつての結婚では、嫁入り道具を揃えることが当たり前でしたが、現代ではその必要性が大きく変化しています。
共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化、さらには経済状況の変化により、昔のように大掛かりな嫁入り道具を用意するケースは減少しました。
しかし、新生活をスムーズに始めるためには、ある程度の準備が必要であり、その内容は夫婦ごとに異なります。
この章では、現代の結婚生活における嫁入り道具の役割や、必要かどうかを判断するポイント、自分たちに合ったアイテムの選び方について解説します。
伝統にとらわれるのではなく、自分たちにとって本当に必要なものを見極め、賢く準備を進めることが大切です。
現代の結婚生活と嫁入り道具の役割
昔と比べると、結婚の形は大きく変化し、それに伴い嫁入り道具の必要性も低くなっています。その背景には、以下のような理由があります。
- 共働き世帯の増加
- 実家の経済状況の変化
- 新生活に必要なものの変化
かつては、結婚すると女性が家を守ることが一般的であり、生活に必要な家具や家電を実家が用意するのが慣習でした。しかし、現在は夫婦共に仕事を持つケースが多く、結婚後も収入を得られるため、必要なものを二人で選び、徐々に揃えていくスタイルが主流になっています。
また、住宅事情の変化により、大家族で暮らすことが少なくなり、新居のスペースに合わせてコンパクトに暮らす意識が強くなったことも嫁入り道具の変化に影響しています。
昔は婚礼家具や着物が嫁入り道具の中心でしたが、現在は家電や収納家具、インテリア用品などが重視されるようになりました。スマート家電や省スペース家具など、現代のライフスタイルに合ったアイテムを選ぶことが一般的になっています。
このように、結婚に対する価値観が変化する中で、嫁入り道具の役割もまた、実用性を重視する方向へとシフトしているのです。

必要かどうかを判断するためのポイント

「嫁入り道具を準備すべきかどうか」は、一概には決められません。以下のポイントを考慮しながら、自分たちにとって必要なものを見極めましょう。
- どこに住むのか(実家近くか、遠方か)
- 夫婦のライフスタイル(共働きか、専業主婦・主夫か)
- 新居の広さや設備(すでに家電が揃っているか)
- 経済状況(無理なく準備できるか)
実家の近くに住む場合、必要になったときに持ち帰ることができるため、最初からすべてを揃える必要はありません。
しかし、遠方に住む場合は、家具や家電をあらかじめ準備しておいたほうがスムーズです。
ライフスタイルによっても必要なものは変わります。共働きの場合、便利な家電(食洗機、ロボット掃除機、時短調理家電など)を優先的に揃えると負担が減ります。
専業主婦・主夫の場合は、料理や家事を快適にするためのアイテムを充実させるのも良いでしょう。
賃貸マンションなどでは備え付けの家電があることもあるため、不要なものを買わないよう事前に確認しましょう。
新築や購入した家に住む場合は、収納や間取りを考慮しながら最適な家具・家電を選ぶことが大切です。
すべてを一度に揃える必要はなく、優先度をつけて少しずつ購入するのも賢い選択です。親が援助してくれる場合でも、必要なものと不要なものをきちんと話し合いましょう。
合わせて読みたい
自分に合った嫁入り道具の選び方

以下の方法を参考に、自分に合った嫁入り道具を選びましょう。
- 実用性を重視する
- 二人で相談しながら決める
- 結婚を機に買い替えを検討する
- ギフトや親の援助を活用する
嫁入り道具は、必ずしも「揃えなければならないもの」ではありません。
しかし、 新生活をスムーズにスタートさせるための準備 は必要です。
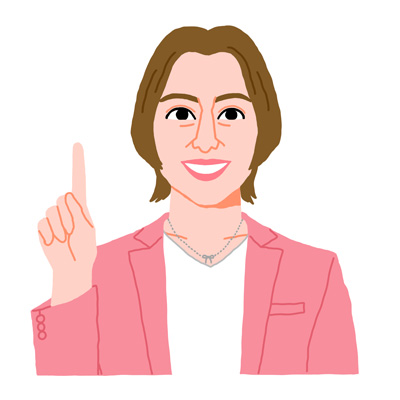
合わせて読みたい
初めての方は、「とよ婚。」無料相談、無料お試しマッチングから

結婚相談所に興味はある方でも、いきなり入会するのはハードルが高いものです。
WEBサイト内の情報だけではわからないことや、お1人おひとりの環境や恋愛事情など様々な疑問があることと思います。
とよ婚。ではご入会前には「無料相談」をさせて頂くことをおすすめしております。
結婚相談所の仕組みだけではなく、婚活においての不安点や恋愛観など様々なご相談をお受けしております。
婚活においてご成婚という結果に行きつくためには、ご自身が納得して活動することが絶対条件です。
些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご連絡ください。
また、まずは「婚活をしてみたいけど、どのような仕組みかわからない」「希望する相手がいるのだろうか」「自分自身を希望してくれる相手はいるのだろうか」といった方向けに、相手への希望やご自身のプロフィールをお伺いし、お相手候補がどの程度いるかをご紹介する「無料お試しマッチング」も提供しています。
婚活をはじめる前に活動のイメージをもっていただけますので、こちらも是非ご活用ください。
まとめ
嫁入り道具は、時代とともに変化しています。昔は実家の格式を示すものとして重要視されましたが、現代では実用性を重視した形に変わりました。
現代の嫁入り道具は、昔のように格式を示すものではなく、 新生活をスムーズに始めるための実用的なアイテム に変化しています。
家電、家具、日用品などを中心に、二人のライフスタイルに合ったものを揃えることが重要です。今のライフスタイルに合ったものを選び、新生活をより快適にスタートさせましょう。
また、結婚後は冠婚葬祭への出席機会も増えるため、礼服や数珠などのフォーマルなアイテムも用意しておくと安心です。
新生活の準備は、結婚を迎える二人にとって大切な時間です。ぜひ、お互いの価値観を尊重しながら、必要なものを揃えていきましょう。
合わせて読みたい